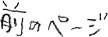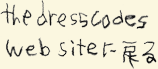昨夜、このブログが無事に開設されたのを見届けて、ぼくは友達とすっかり酔っぱらってしまうことに決めた。
少しおおげさに始めてしまった気もするし(バンドマンが日記なんて、とぼくはいまだにそう思うし)それでも、これから始まるここでの試みを思うと、どうにも興奮が治まらないのだった。
つまり、夜にお酒を飲みに出るには十分な口実があったワケだ!
雨が降る中を少し歩いて、明け方に家に帰った。
パソコンを開くと、すでに山のような返事が届いていた。
それも、さっきまでには全部読んでしまった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日の「まえがき」で、ぼくはこんなことを書いた。
《ぼくはここ1年ほど音楽にだけ見とれていた。他の誰も目に入らないで、それは「かけおち」と似ていた。》
この1年半ほどを、ぼくはなるべく口をつぐんで生きてきたつもりだ。
それは、生まれたばかりの無垢なバンドにぼくの言葉や歴史をかぶせてしまうことをひどく恐れていたからだった。
生まれたばかりの命は無垢で美しく、それゆえに無防備だ。
ほんのわずかな傷や病でも命とりになるだろう。もしもそんなことがあったなら、それはすべてぼくの責任だ、そんなことを考えては躍起になっていた。
きっとこれは、自分がバンドをひとつ失っているからかもしれない。
そうして生まれた1stアルバムは、ぼくらがぼくらのためだけに作ったものだ。誰のためでもなく、ただぼくらのためだけに書かれ、演奏されたものだった。
こんな「かけおち」の季節に、その時のぼくは『1954』と名前をつけている。
1stアルバムのラストに収録した曲であり、またドレスコーズが初めて経験したツアーのタイトルでもある。
あのツアーでぼくらの音楽は、果たして誰に届いていたんだろうか。
ぼくらの目の前にいた大勢の人たちの顔が、今なぜかまったく思い出せないのだ。
ぼくが書いた歌はぼくによって歌われ、それをぼくだけが聴いていた。
まるで宛先不明で返ってきた手紙のようだった。
ステージから見る客席はいつだって闇の中だ。
ぼくはいつも、ぼくの歌を誰が聴いているのか知ろうとし、結局それは最後までハッキリと見えない。
真っ暗な客席、宛先不明で返ってきた手紙。
これが1954年のぼくの記憶になっている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このファースト・ツアーは、ぼくを大きく変えた。
その後、バンドは新たな制作にとりかかり、まず “We are” や “シネマ・シネマ・シネマ” 、 “ハーベスト” そして “トートロジー” といった曲が生まれた。
そのどれもが驚くほどストレートで、特別な響きをもった曲ばかりだった。
そして同時にぼくらが取りかかったのは、次の新たなツアーの企画だった。「VS SERIES」と銘打った、ツーマン・ツアーの開始である。
ライブハウスで育ったぼくらは、二組のバンドが先攻・後攻でぶつかる、いわゆる「ツーマン形式」が持つ緊張感と興奮をよく知っている。
自分たちだけのワンマンライブか、もしくは一挙に何組ものアーティストが出る大型フェスしか経験していないぼくらは、あの緊張感と興奮の中で、忘れた記憶のようなものを必死に取り戻そうとしていた。
そして新曲も試すうちに、いつしかぼくは昔のように真っ暗な客席に足を踏み入れて歌うようになっていた。
そうなのだ。
ぼくが見てきたステージからの景色は、いつだって真っ暗だった。
目の悪いぼくにはいつもそう見えていた。
だから客席によく飛び込んでいたのだ。
ぼくは今度こそ知ろうと思った。
ぼくの歌を、一体誰が聴いているのかを。
ドレスコーズは、もう「ぼくが守るべきバンド」なんかではとっくになくなっていた。
あの暗い客席の中にいる、誰かのものになっていたのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そう、これがぼくが日記をつけ始めたもうひとつの理由だ。
つまり、きみとぼくが、細かいことのひとつひとつまでちゃんと覚えていられるように!
さて、ぼくはここで、きみに向けてくだらないことをたくさん書くだろう。
わずか数行しか書いてないで、ガッカリさせる日もあるかもしれない。
そしてたまに、書くべきかどうか悩むようなこんな話も打ち明けてしまうだろう。
それでいいと、今は思っている。
ぼくはバンドマンで、これは日記なのだから。
それでは、きみに握手を。
今日はこの日記を書くことに1日を費やしてしまった。
連載〆切、明日には書くこと。
日本語のドレスコード
ドレスコーズを殺すな。
2013年09月25日 20時56分